|
好きな散歩道にある、ヤギ小屋。 山の結構な斜面にあって、とても景色の良い絶景地点にあります。 (注:写真は豪雨より以前です。まだ散歩に行けてません。) この写真を撮った時、ここのすぐ近くで、ピクニック中の親子4人がシートを広げて 楽しげにお弁当を食べていました。 ヤギ小屋はなぜか臭くありません。高原でのんびりと牧草ばかり食べているからでしょうか。 臭いがしても、牧草が発酵したような、草の香りです。 一帯が牧草だし、おひさまと草の香りがしています。 子ヤギがよく柵の外でウロウロしています。 体が小さくてうまい具合に外に出られたものの、その場所がわからなくなり、戻れなくなるようです。 右の子ヤギのように、柵の網に何度も何度も頭を突っ込んでいるのを見ました。 (゜д゜;) 「逃げられないように、もっと目の細かい網にしなくちゃ。」 飼い主はなぜそんな当たり前のことをしないのかと驚きました。 私はヤギを飼ったこともないのに、自分の考えのほうが当然だと思ったのです。 それで「いつも子ヤギが外にいて、あの柵、ダメだよね。」などとダンナくんに話してみたところ、 理由を教えてくれました。 (^⊆^) 「子ヤギは、親から離れません。 外へ出られても、遠くへ逃げないんです。 だから、親が外に出られない柵にすれば、問題ないです。」 ああ、なるほど。そういう理由なのか。(///∇//) ここでは子ヤギがウロウロしていても、散歩に来た子供が喜ぶくらいで、確かに何も問題はないのです。 この辺りでは動物の習性を利用して「こうすると車は通れても、牛はこの道を通れない。」とか、酪農・放牧地帯ならではの、いろんな知恵があります。広大な敷地に多額の費用をかけて柵などを全て完璧に作らなくても、全く問題ないのです。
それなのに、牛もヤギも飼ったことがない私が、しかも農耕文化の国から来た私が「この柵はちゃんと直したほうがいい!」と酪農文化の場所でとっさに思ったことに、自分で苦笑してしまいました。 私は何を知っているつもりなんだろう? 外国でもまあだいたいこんなもんだろう、という想定と違うことは多々あります。 異文化の、異国の人間が、私のちっぽけな知識の範囲で思うことなんて、こんなもんです。 全てにあてはまることではないけれど、自国には自国の、外国には外国の、それぞれの文化に理由があって、外国人の意見を聞いたり、外国の文化を取り入れるのも、文化背景も考慮した取捨が必ず必要だとしみじみ思います。 日本は歴史的に見て、外国の文化の良さを柔軟に取り入れる能力が非常に長けていますが、現代ではそれが一部、消化不良をおこしているような気がします。 昔は異文化が普及するまで時間を要したため、ひらがなのように自国の独自文化にまでなり得た訳ですが、ネットが普及した現代では、異文化の情報が急速に大量流入しているので、個々の取捨により方々でルールの矛盾や衝突が出る事態が起きても、何ら不思議ではないと思います。 同じ民族で、同じ国籍だろうとも、いろんな国の別々の異文化に共感して影響を受けた人達が、さらに独自解釈で細かく多様化していく様は、まるで多民族国家になっていくかのように思えます。 日本には日本の良さがあるのに、それらの良さには必然的な理由があったはずなのに、その価値は見過ごされて、いつの間にか失くしてしまった良さもあると思います。 変わらなくていいものも、たくさんあったはずなのに。 普段、外国暮らしの中で「これは良いな」と思った異文化を紹介している私のブログですが、 だからこそ、そんなことをヤギ小屋の前で、ふと思ったりするのです。
0 コメント
週末、ずーっとハンパなく降り続けた豪雨。 南ドイツとオーストリアは、今、大変なことになっていて、うちの近くの道路も封鎖されています。 近くの建物は上のほうから大木が降ってきたらしく、屋根が大破しておりまして、ゾッとしました。 無人だったのが不幸中の幸い。 欧州中部、集中豪雨で洪水 4人死亡(AFP通信) http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/disaster/2947535/10839413 このニュースを読んだところ、この週末で2ヶ月分の雨が降ったそうです。 ちなみに、我が家もみんなも無事です。 もう雨も一段落したっぽいです。 最初、事態をわかってなくて、雨が降っているのを眺めながら、ビーバーのことを考えていました。
ビーバーが溺れることはないだろうけど、巣はきっと壊れちゃっただろうな。 同じところにまた巣を作ってくれるかしら。 そうだ、雨がやんだら見に行こう。 そんなことを考えておりました。 逆に、ドイツ、オーストリアは ビーバーに心配されてもおかしくない状況になっとります。 息子が好きな遊び場。 赤いロープで出来た、ジャングルジムです。 私はここで初めて見ましたが、日本にもたくさんあるんですね。 4歳児にはまだ難しい高さなんじゃないかと、最初はハラハラ見ておりました。 ばあさま達が言うには、 「本人が痛い思いをしないと、本当に危険な時、本人が気をつけられない。」とのことで、 子供がある程度大きくなったら、公園は安全だから、危険は教えつつも見守りなさい、みたいなこと言われています。 公園は子供が失敗する前提で作ってあるのか、遊具の下が、「やわらかい土&牧草」もしくはコルクのように柔らかいウッドチップが山盛りひいてあって、落ちてもケガをしないように作られています。 失敗から学べるから、失敗することは良いことらしいです。 失敗して学んだ子供は、褒められます。 親が大丈夫な範囲だと判断した環境で、目の前で失敗してくれたほうが安全で、それは良いことだと考えられているようです。失敗させないように、とはしない大人達のようです。 確かに子供は、一度落ちたところからもう落ちないようです。 親は、親同士のおしゃべりは二の次で、テニスの観覧席のように一列でじっと見守っています。 子供の事故って、一瞬の出来事だから、皆ずっと見続けているのです。 以前から、ベンチの位置が何か変だなと思ってましたが、恐らくそれは子供を見守るための配置です。 私が行く小さな公園では、公園の外にベンチがあって、公園全体を眺める位置にあります。
親はそこのベンチに腰掛けて、デパートのインフォメーション係の人同士みたいに、視線は真っすぐで、隣の相手と顔を見合わせずに、話しています。で、時々、相手の顔を見て、また視線は真っすぐ。 相手の顔を見ながら話すのが重要な文化ではないようで、まず第一に子供を見ています。 (私が行く公園では、です。) じゃあ、全体が見渡せないような、大きな公園ではどうするかというと 親が公園のベンチを持って、子供がいる遊具の前に移動します。 で、プールの監視員のように、真っすぐ見る。(笑) 最初は、ものすんごく驚きました。 ベンチを持って移動するなんて、考えたこともなかったです。 だからその公園では、いつもベンチが転々としていて、どこにあるのかわからない。(笑) ダンナくんに「そんなのアリなの?」と聞いたら、何がいけないの?と不思議そうに聞きかえされました。 外国の文化って、いつも新鮮な驚きがありますね。 |
このサイトに掲載されている、全てのイラスト・写真・画像の無断転載・複製を固く禁じます。(文章についても、引用の範囲を越えた無断転載や、出典を明らかにしていない引用及び、当サイトへのリンク無しの引用も、固く禁じます。)
AuthorAlpenHausfrau Heidi ■免責事項 当サイトに掲載された記事情報及び意見や見解は、個人の感想レベルであり、その内容について何ら保証しません。情報の間違いなどに対して一切の責任を負いませんのでご了承下さい。 Archives
7 月 2020
|

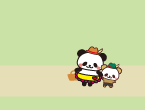








 RSS フィード
RSS フィード
