|
昔、会社員としてデザインをしていた若い頃。業界的にはわりと有名な賞に応募したことがある。
それは「カンプとして会社に出しても100%スルー間違い無し!」な、商業には全く向かないようなヘンテコな個人的作品での応募。完成した絵を見て、自分では「おもしろい」って思ったから、とりあえず知らない人に実物を見てもらいたかった。この絵を見て他の人はどう思うんだろう?著名な審査員たちがどう思うのか知りたくなった。 忙しい毎日でそんな試みを忘れた頃に、落選を知る。そうか、この絵、変だもんな。当然のこととして受け止めて、作品の搬出に行った。すると係員が「ちょっと待って」と奥に引っ込んだ。私の作品は最終選考まで残ったから別で保管してあって、推してくれた審査員のメッセージが残されているという。 その内容を大まかにいうと、なぜ受賞することができなかったのかという理由と、個人的な意見、の2つ。 前者のほうは「どこかで見たことがあるような気がする。」 全くのゼロから思いつきの落書きから生まれて自分で描いた完全オリジナルだったし、こんな意味不明なヘンテコ絵を描く人って他にいるか〜??って疑問に思ったけど、すでに私は職業として自分のイラストデザインの商品が日本全国及び海外で販売されていたし、同じ人間が描いてて作風自体は同じだったし、その審査員がどこかで私の絵を見た事があってもまあ不思議ではなかった。そんなことになるとは思わなくてプロフィールはちゃんと書いてなかったと思う。 そして、目新しさに左右されるのであれば、この先、何に応募しても受賞は無理だと思った。何を描いても、私の絵は、どうしても私になってしまう。この先の未来を宣告された気がした。 仕事から離れて前衛を気取っても、どことなくやっぱりどこかで見た商品っぽい印象になる気がする。というか、入社前から商品っぽい絵で、しかも先輩から「どうしてうち(の会社)っぽいの!?」と言われてた。子供の頃からここの会社の商品が大好きだったから、これしか描けない。 他人の作品を模写して練習しても、自分で「いい!」と思える習作は一度も作れなかった。 モニター会で子供たちに「私にも描けそう」とよく言われてたけれど、本当は、完コピはプロでもゼロから描けないことも知っている。オリジナリティはある。ファンもいる。子供向け文具雑貨なのに、サラリーマンが立ち読みしていたと営業さんから聞いた。でも私の絵はこのままでいいんだろうか。自分の狭い技量にガッカリしながら後者の「個人的な意見」のほうを読んで、ハッとした。小さな紙にポツリと残されていた内容は、 「部屋に飾りたいと思った。」 私にはもうそれで十分だった。そのほうが、本当の受賞である気がした。 どういうジャンルの作品だろうと、「賞」というものには、少なからず審査員の「建前」があると思う。 世間に対して「これは受賞に値するだけの価値があります。」と、自分の名声を担保として宣言できるだけの理屈を準備してから決定している。販促の意味での受賞や、師弟制による受賞などだけでなく、純粋に評価を受けた作品も、公募である限り第三者への説明が普通は必ず必要だからだ。 つまり、その理屈という「正解」に自分を当てはめることができれば、受賞の確率があがる場合がある。 それと同時に、「研究しやがって」という失笑の確率もあがると思うけれど、それでも、だ。 文学や美術に「傾向と対策」があるのは悲しいことだけれど、そういう方法が世の中にはあって、最短距離を行きたがる人達の中には、それを研究する人もいるはずだ。 そのロジックを既に身につけている審査員たちは、別の賞の一応募者となっても受賞しやすいのは、無理からぬ話だと思う。審査員経験者は、審査員の正解を察知する能力が高くなっていると推測する。 晴れて世間に認められたマーケティング系アーティストの代表といえば、村上隆さんだと思う。彼の著書を読んだことがあるけれど、彼はなんと修羅の道を選んだことか。 美術界的に意見は様々だけれど、彼が過去に生み出したものはアートに分類されると私は思う。(近年の作品はよく知らない。)確かに新しいことをして、新しい文脈をつくった。それが海外で評価されたのはわかる。 ただ、その道は、辛い人生だろうなと、今は思う。
話を戻すと。
そのしばらく後、その最終審査で落選した絵たちを堂々と並べて、某所で個展をした。 私はその絵たちが好きだったから、全く知らない誰かたちにもやっぱり見てもらいたかった。 開催期間中、その中の1枚をなぜか何度も何度も観に来る不思議な人がいて、そのうち友達をつれてきて2人で何か熱く語ってたりしてて、でも私は話すこともないから放っておいたのだけど、最終日に初めてその人が私に向って声をかけてきた。 「この絵、売ってください。」 「え、これ、売ってません。ごめんなさい。 そんなに好きになってくれて嬉しいです。ありがとうございます。」 「いや、そういうんじゃなくて。この絵、売ってください。」 その人は私の「嬉しい」なんてどうでもいいんだよ、とでも言いたげな全面イライラを押し殺しもせずに、ただただ、その絵を欲しがっていた。その人は純粋にその絵が好きだったんだと思う。写真を撮りたいとさえも言わず、熱烈に原画を欲しがった。確かに、大事な表現のひとつだった紙質の再現までは、スナップ写真では難しいと思う。 これは最終選考に残った絵で、審査員の某さんに部屋に飾りたいって言ってもらった絵で思い入れのある絵だし、私も好きだから売れません、などと説明したけれど、諦めてくれず、結局、「同じ紙で、全く同じ絵をもう一枚描いて、それを後日売ります。額装なしで5万円。」ということで納得してくれて、交渉がまとまった。その絵はほとんどのスペースが何も描いてない余白ばかりで「紙がきれいだよね」みたいな絵だったけれど、それが私の絵画作品の初めての値段だった。 そんなにこの絵が好き??って嬉しかったけれど、全く同じ絵を絵の具でまた描くのか…と目眩がした。パンを何個も焼くのとはわけが違って、とんでもなく退屈なことを引き受けてしまった。何度も描かなくて済むのに欲しい人たちみんなが部屋に飾れる「印刷」って素晴らしいなと改めて思ったのもこの一件が原因。文明万歳。 あなたの考えは商業的すぎる、と純粋芸術な古い人達からは軽蔑されがちだけど、工場で大量生産されることや、デジタル作品に、私は全く抵抗ない。全部、私がつくったものだよ。 その後、私は結婚したり、子供をうんだり、海外で暮らしたり、私はいろいろ変化していった。 そして周囲も変わっていった。いつまでも学生みたいに好きなことをするのを、他人は許してくれなくなった。 身近な人達、家族や友人たちは応援してくれてるのに、何の迷惑もかけない人たちになぜ許しや説明が必要なのか不思議だった。そういう何だかよくわからない問題も理解し、対応して、徐々に解決していった。 他人の意見、他人が自分に勝手につけたラベル、他人の都合による評価。 それを気にしたり、意見が違う人とケンカしたり、落ち込んだこともあったけれど、 そんなものは、全て、どうでもいいものだった。 牛や鶏たちが放牧される土地で、羊にまっすぐ見つめられた。 「お前はなんだ?」 そうだね、私、今まで何を気にしてきたんだろう。 自分が楽しい好きなことをやって、自分の中での葛藤から、ある日スッと解放された。 何も考えてなかった遥か昔の頃のように、自分が好きなものをつくろう。 できあがったら、自分の部屋に飾ろう。 自由に好きなものを描こう。自分が追い求める、いろんな作品をつくろう。 バカにする人はバカにしてもいい。その人のためのものじゃない。私のためのものだ。 などと、ご大層な決意とは裏腹に、私の頭は相変わらずくだらないことが大好きで、頭に浮かんだこんなものを、思いつきで描いた。「哲学ラトル」。 ベビー用品の熊が、ヒゲ付けて哲学語ってて、気に入った。アホらしくて、かわいい。 (ちなみに、写真は商品撮影写真を元にしていますが、もちろん合法利用です。念のため。) 何度も見ているうちに、誰かに見てもらいたくなった。全く知らない他の新しい世界にこの熊を出してみたいな。アメブロとかじゃなくて、全然違うところに…。 そう思って、新たに登録したのが、noteっていうサイト。 私のページはこれ。 https://note.mu/alps (注:個人サイトで掲載したものを転載しただけで、今のところ私の新しいコンテンツはありません。新たに登録する必要はないです。) どうせ何を描いても私になっちゃうんだから、「ハイジ」っていう名義(?)を消してこっそりやるつもりはなくて、でもブロガーとかそういうのは出さないで、知らない人に単純に画像を見てもらおう、文章はごく最小限にしよう、そう思って、ひとまず前出の「哲学ラトル」を登録。よし、第一歩。 誰をフォローしようかな。 「おすすめ」にあがってた中に、小説家の平野啓一郎さんを発見。 新聞で連載中の新作小説を、海外でもネットで無料で読める?! すごいことしてるなー。素晴らしい挑戦。 敬意をこめて、そして、新作小説が読めることがうれしくて、もちろんフォロー。 よし、新しい第二歩目。 すると、しばらく後に、誰かが初フォローしてくれた。 フォローじゃなくて、フォロワーよ?! これを書いてる今現在、私が描くものは平野さんとマンツーマン状態……∑(@Д@;どどどどういうことなのよ! ありえない奇跡にガクブル。 フォローしてくれた人を全員フォローしてくれる人なのかなと、ガクガクしながら確かめたら、約1,800人からフォローされてるのに、14人フォローしかしてなくて、ひっくり返るかと思った。SNSってすごい世界だなって、初めて思った。芥川賞作家が、私のギャグ読んでくれたって、なんてすごい時代なんだ!って、今さら! やっぱデカルトのおかげかなー。それともアルプスのおかげかなー。次アップしたら、私の描いたものがタイムラインに流れちゃうんだなーと思ったら、文章はあまりにも恥ずかしくて絶対目にふれちゃいけない!って思って、noteではやっぱり視覚的にがんばっていこうと再決意。いや、頭のいい切れ者な友人たちと昔から話してるから、全てお見通しすぎてミジンコみたいに自分が全てスケスケなのは慣れっこで、そういう友達たちにも昔からブログも読まれてるから、自分のアホな面もダメな面も今さら文章からも隠すつもりはないんだけど、作家は別格なのよー。てにをはから恥ずかしすぎる!うわーうわー。 落ち着け私。自分がつくるもので、誰かにたまたま気に入られたとして、次のものが違ったとして、フォローがなくなったとしても、それでもいいんだ。誰かのために作るんじゃないから。好きなものを世の中に発表していくんだ。 フォロワーがゼロでもいいんだ。外されてもいいんだ。よし。 最初は「ドイツアルプス地方に住んでます。」とだけ書いていたプロフィールを少し修正して、「作品をつくってます。」にした。遠慮することはない。どんどん行こうぜ、私! 平野さんはたぶん気軽にポチッと押してくれたんだろうけれど、小さな私の背中を押してくれた。 こんなことって、あるんだ。 ネットネイティブにとっては「何を驚いてるの」って、きっと今時こんなことって軽く日常茶飯事なんだろうけど、私の友達も「ネット見る暇があるなら本読むわ!」っていう硬派が多いためmixiすら参加せず、SNSは苦手だから、本当に驚きだった。 あーこんなに照れたの、子供の頃くらいじゃなかろうか。 勝手な自己解釈だけど、「わたし、好きなことを続けてもいいんだ」って思えた。 それと、後輩から聞いた嬉しい話。 入社した新入社員が、子供の頃に、私が作った商品が好きだったそうで…。 私も子供の頃に好きだった会社に入社したように、その人も私の作ったものの影響も一部あって入社を決めたのだとしたら、私も先輩達から受け継いで誰かの背中を押せたのかと、役目を果たしていたのだと思った。 そして同時に、私ってそんなに年をとったのかとも思った。爆。 これからも、商品だろうと、個人的作品だろうと、どちらも堂々と作り続けていこう。 などと、自分一人語り。 こんな長い一人語りをよくぞここまで読んでくださいました。感謝です。 そして、平野さんへ私ができる超ささやかなお礼に、とりあえずその新作小説の目次をリンク。 海外からも(とりあえずドイツからは)無料で読めるから、ごらんあれ〜。 海外だとやっぱりちゃんとした日本語の活字には飢えてて、本当に嬉しかった。Kindleの本って意外とまだ少ない。 「マチネの終わりに」目次 https://note.mu/hiranok/m/m5f19f44b93c9 昔、頭に焼き付いた「京大法学部在学中に芥川賞受賞」という華々しいイメージがあまりにも強くて、何でも思いのままに進めそうな順風満帆な人生いいなーと単純に思ってたのだけど、大人に成長した今の私は、それがいかに大変な道であったであろうことに気づく。何才になっても進化していける人が好き。著書をいろいろ読んでみよう。 他、最新刊など書籍リンク。ではまたー。私もがんばろっと。
0 コメント
あなたのコメントは承認後に投稿されます。
返信を残す |
このサイトに掲載されている、全てのイラスト・写真・画像の無断転載・複製を固く禁じます。(文章についても、引用の範囲を越えた無断転載や、出典を明らかにしていない引用及び、当サイトへのリンク無しの引用も、固く禁じます。)
AuthorAlpenHausfrau Heidi ■免責事項 当サイトに掲載された記事情報及び意見や見解は、個人の感想レベルであり、その内容について何ら保証しません。情報の間違いなどに対して一切の責任を負いませんのでご了承下さい。 Archives
7月 2024
|


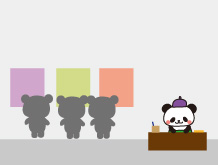





 RSSフィード
RSSフィード
